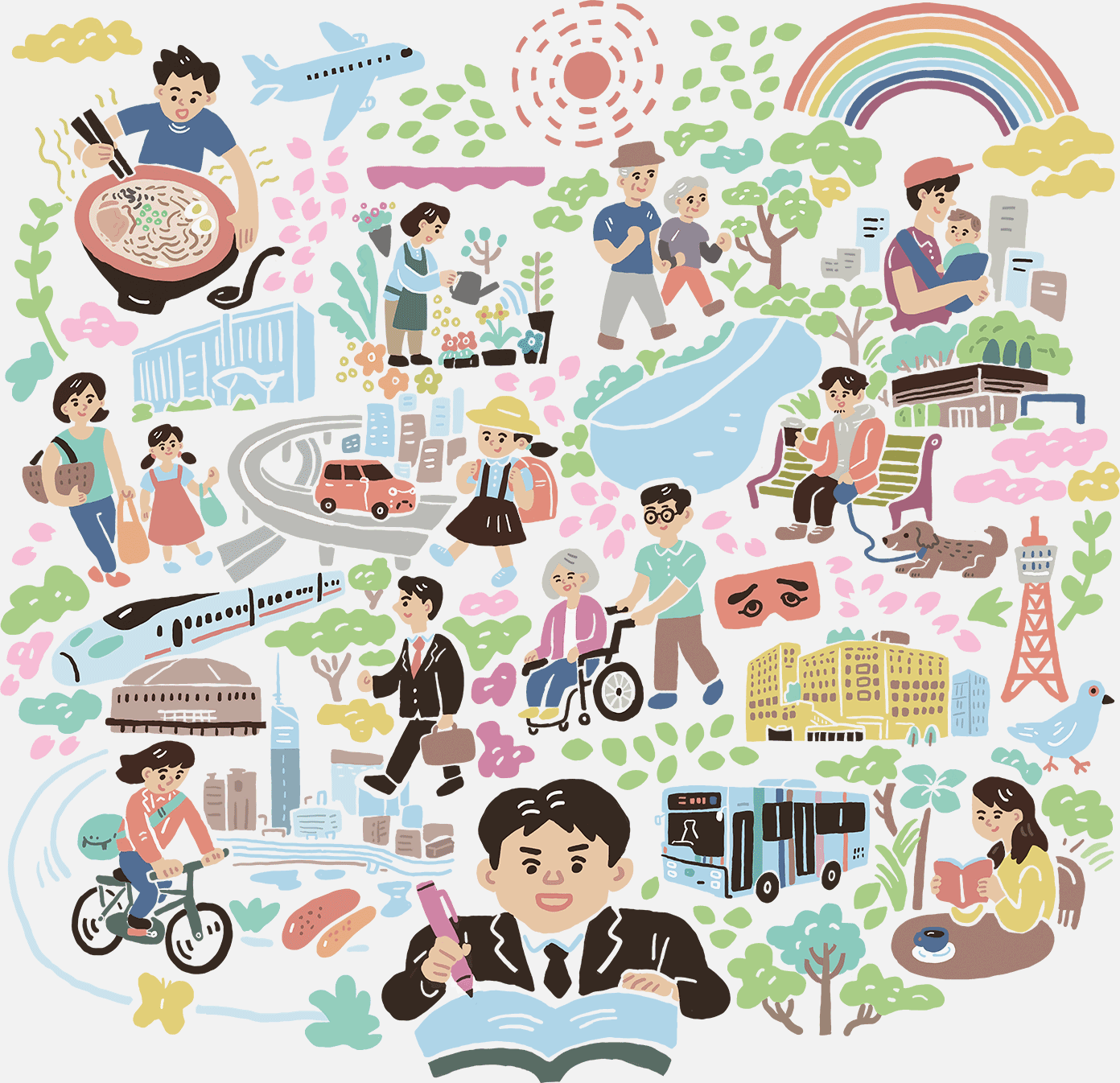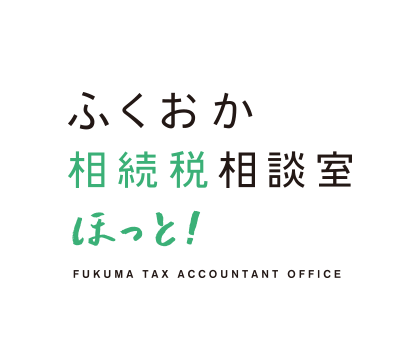知っておきたい「相続税」と「贈与税」の違いとは?仕組み・税率・節税方法までわかりやすく解説
相続税と贈与税は、いずれも財産を取得した際に関わる税金ですが、その発生時期や計算方法、適用される非課税枠や優遇措置には大きな違いがあります。
この記事では、福岡で相続や贈与を検討している方に向けて、両者の違いや注意点、節税対策のポイントまでをやさしく解説します。
相続税と贈与税の違いを比較【一覧表】
| 比較項目 | 相続税 | 贈与税 |
|---|---|---|
| 財産取得のタイミング | 被相続人が亡くなったとき | 生前に財産を譲り受けたとき |
| 課税される人 | 相続人や遺言で財産を受け取る人 | 財産を受け取った側(受贈者) |
| 非課税枠 | 3,000万円+600万円×法定相続人の数 | 年間110万円(暦年贈与の場合) |
| 税率の仕組み | 最大55%の累進課税 | 最大55%の累進課税 |
| よく使われる特例 | 配偶者の軽減、小規模宅地等の評価減など | 相続時精算課税、住宅資金贈与の非課税制度など |
| 申告期限 | 相続発生から10か月以内 | 翌年3月15日まで |
相続税とは?亡くなった方の財産を受け継ぐときの税金
相続税は、被相続人(亡くなった方)から不動産や現金、株式などの財産を相続した場合に課される税金です。
福岡市内でも、地価や不動産評価額によって相続税の申告が必要になるケースが増えています。
主なポイント
-
法定相続人が2人なら最大4,200万円まで非課税
-
配偶者は最大1億6,000万円まで無税で相続できる
-
不動産の評価が下がる「小規模宅地等の特例」がある
-
生前からの相続対策が効果的
贈与税とは?生きている間に財産を渡したときの税金
贈与税は、親族や第三者から金品・不動産などを無償でもらった場合にかかる税金です。納税義務は受け取った側にあります。
主なポイント
-
年間110万円までなら非課税(暦年贈与)
-
まとまった金額には高い税率が適用される
-
記録や贈与契約書などの証拠が重要
-
相続税より不利になる場合もある
どっちが有利?相続と贈与の使い分け方
「結局どちらが得なのか?」は状況次第ですが、以下のような考え方が参考になります。
贈与が向いているケース
-
子や孫に毎年コツコツと教育資金などを渡したい
-
相続時の財産評価を減らしておきたい
相続が有利な場面
-
配偶者が財産を受け取るとき(1億6,000万円まで非課税)
-
特例制度を活用して節税できる場合
相続時精算課税制度とは?贈与税を抑える有効な手段
「相続時精算課税制度」は、60歳以上の親から18歳以上の子・孫への贈与が対象で、最大2,500万円まで贈与税がかかりません。
その代わり、その金額は将来の相続時に加算されて精算される仕組みです。
利用の注意点
-
一度選択すると暦年課税には戻せない
-
長期的な資産移転計画が必要
福岡で相続・贈与を検討する方へ|早めの準備で節税に差がつく
相続税と贈与税は、どちらも家族への財産移転に関わる重要な税制度です。制度の特徴や特例を正しく理解し、将来に備えることで、税負担を抑えることが可能です。
✅ まとめ
-
相続税は死亡時に課税され、非課税枠や特例が多い
-
贈与税は生前の財産移転に課税され、毎年110万円まで非課税
-
状況に応じて「相続時精算課税」などの制度を使い分けることが重要
![]()
税理士・福間より
生前贈与は相続対策として有効な面もありますが、住宅など高額資産の贈与には注意が必要です。
地価がある程度高い地域では、相続時に「小規模宅地等の特例」を活用する方が、結果的に節税になるケースが多く見られます。