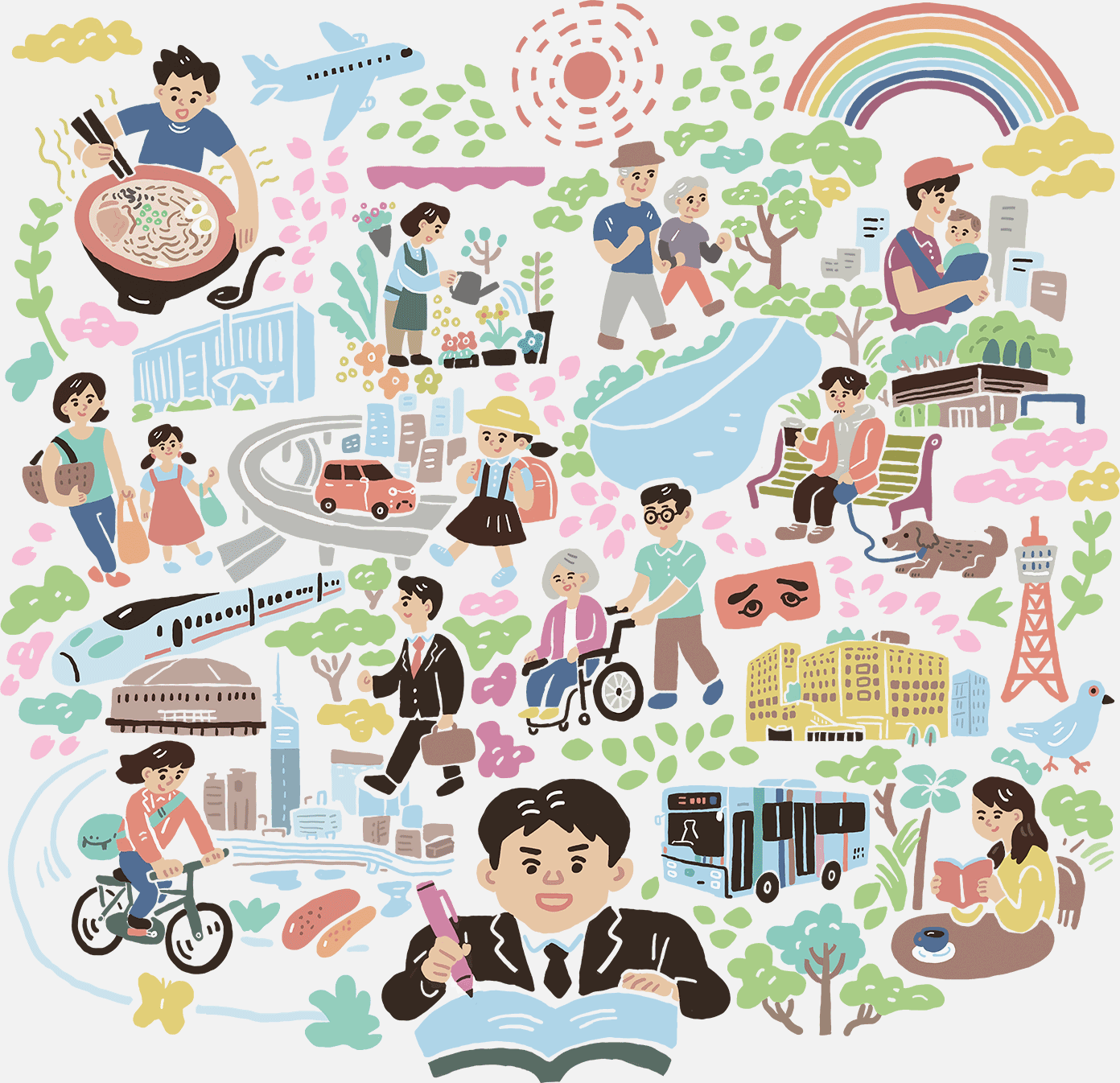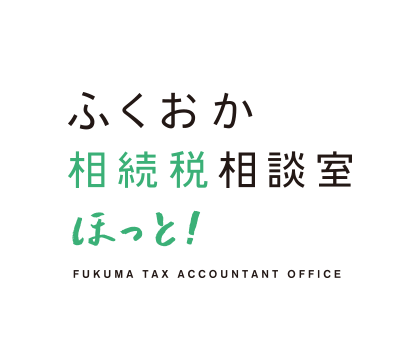相続税の申告が必要かどうかを判断する上で、最も重要なポイントのひとつが「基礎控除」です。本記事では、税理士の立場から、基礎控除の概要・計算方法・よくある誤解・注意すべき特例などをわかりやすく解説します。
基礎控除とは?相続税がかかるかどうかの「境界線」
相続税の課税対象となるかどうかを判断する際、まず最初に確認すべきなのが「基礎控除額」です。遺産総額がこの金額以下であれば、基本的には相続税の申告も納税も不要です。
◆ 現行の基礎控除の計算式
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
この計算式は平成27年(2015年)以降に適用されているもので、それ以前の「5,000万円+1,000万円×法定相続人」から大きく引き下げられています。
【早見表】法定相続人の数別・基礎控除額一覧
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
この基礎控除を超える場合には、相続税申告が必要になる可能性があります。
法定相続人の数え方に注意
意外と見落とされがちなのが、法定相続人の正確な人数の把握です。以下のポイントに注意が必要です。
● 相続放棄した人も「数」に含める
相続放棄していても、もともと相続人に該当していた人は人数に含めます。
● 養子の扱いに上限あり
養子がいる場合は、実子の有無によって含められる人数に制限があります。
-
実子あり:養子1人まで
-
実子なし:養子2人まで
相続税が減額される規定とは?
基礎控除額以下であれば、原則として申告も不要ですが、以下のような場合も無税となる可能性があります。
● 配偶者の税額軽減
配偶者は「1億6,000万円」または「法定相続分」までの財産を取得した場合には相続税がかかりません。
● 小規模宅地等の特例
居住用・事業用の土地については最大80%まで評価減されることがあり、相続税が発生しないケースも多くあります。
● その他の控除
未成年者控除、障害者控除、相次相続控除など、個別に適用される制度もあります。
よくあるご質問(Q&A)
Q. 基礎控除を超えたら必ず相続税がかかりますか?
A. いいえ、控除を超えていても、各種特例や控除の適用により納税額が0円になることもあります。
Q. 相続税の申告が不要な場合、申告書の提出はしなくて良い?
A. 基礎控除以下であれば提出義務はありません。ただし、配偶者控除や小規模宅地の特例を使うには申告が必要です。
![]()
税理士・福間より
当事務所では、初回相談無料で相続税診断も行っておりますので、お気軽にご相談ください。