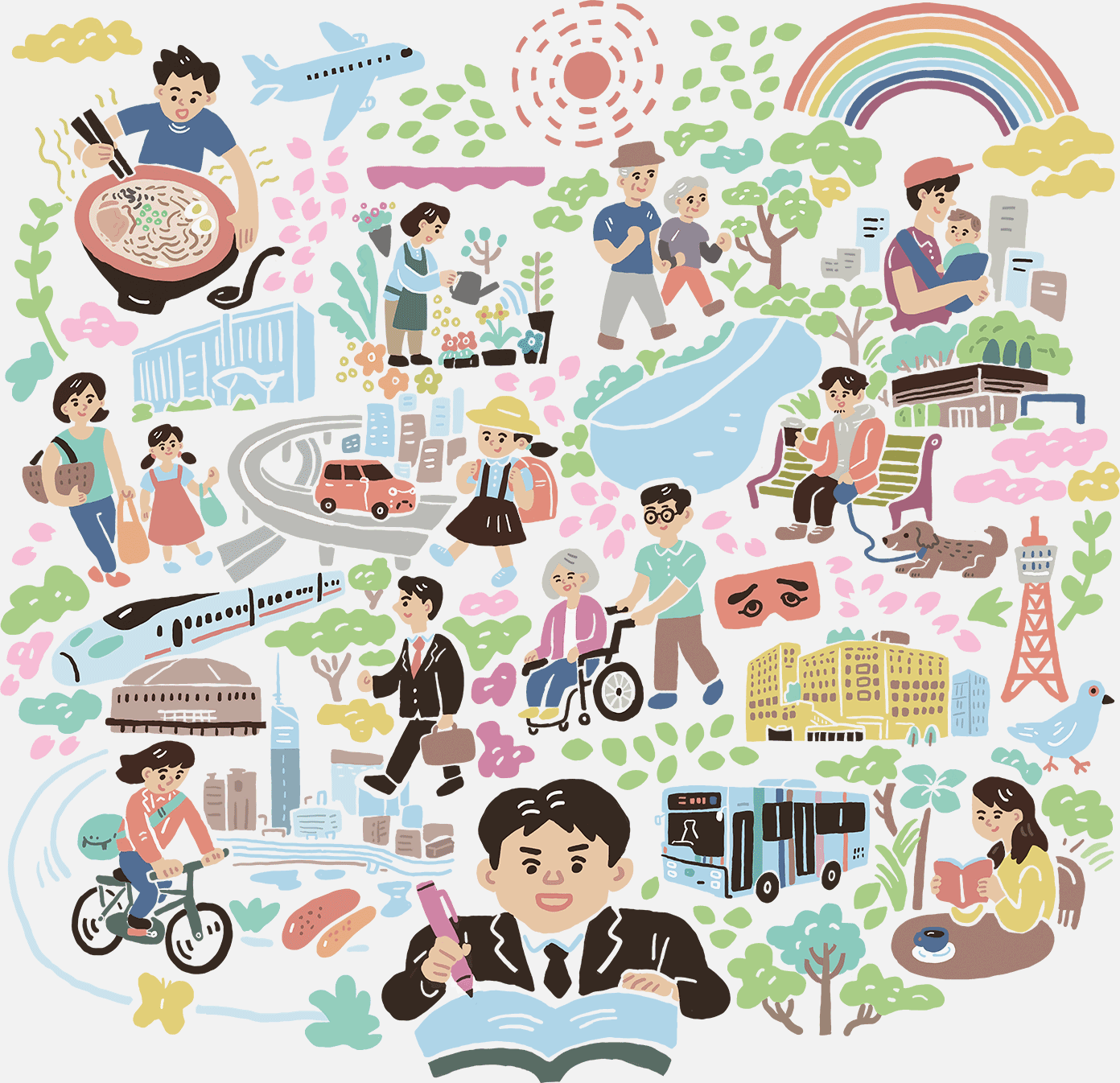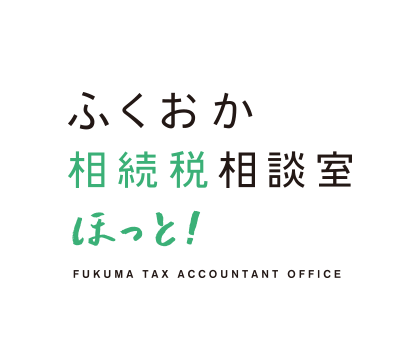「うちは相続税なんて関係ないと思っていたのに…」
そんな相談が増えています。
相続税が発生するかどうかの「境界線」となるのが基礎控除。この記事では、申告の要・不要を見極めるうえで知っておくべき基礎控除の計算方法と、よくある“落とし穴”を税理士がわかりやすく解説します。
そもそも「相続税の基礎控除」とは?
基礎控除とは、相続税の対象になる「課税遺産」を計算する前に差し引かれる非課税枠です。この金額以内であれば、相続税の申告・納税は不要です。
▶ 計算式
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
▶ 具体例(相続人が子2人の場合)
3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円が非課税枠
遺産の正味額が4,200万円以下であれば、相続税の申告は不要になります。
基礎控除だけでは判断できない!見落としがちな3つのポイント
① 「名義預金」や「保険契約」が含まれているか
「生前に母が子の通帳に単に移していた貯金」や、「亡くなった人が保険料を支払っていた保険で、被保険者が相続人になっている保険」なども、相続財産とみなされることがあります。
② 相続放棄した人もカウントする?
基礎控除の計算では、相続放棄をした人も「法定相続人の数」に含めるため、控除額に影響します。
→ 放棄した人数によっては申告義務が変わることも。
③ 遺産の評価方法で結果が変わる
不動産や未上場株式の評価方法によって、遺産総額は数百万円~数千万円単位で増減します。
→ 市場価格ではなく税法上の評価で判断する必要があります。
「非課税だと思っていた」が一番危ない
特に以下のようなケースでは、実際には申告が必要だったという事例が多く見られます。
-
亡くなる直前に通帳から引き出して、手元においていた現金をカウントしていなかった
-
配偶者や子供の預金に、単に移動させた預貯金をカウントしていなかった
-
数年前に贈与された預金が相続財産に加算された(生前贈与加算)
![]()
税理士・福間より