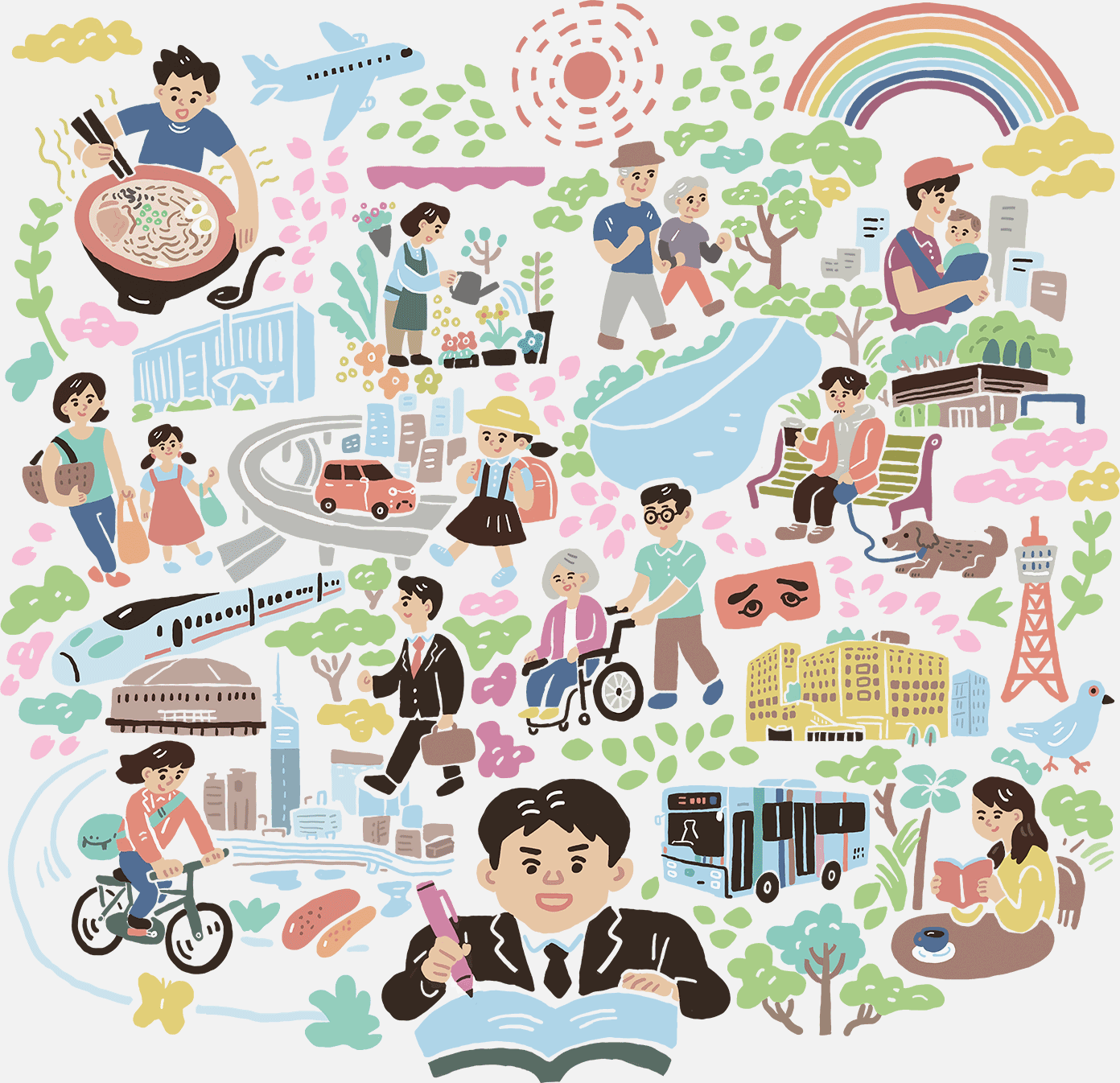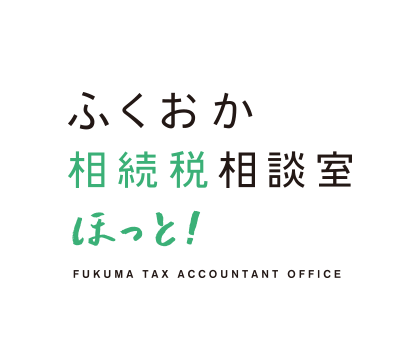相続は、ある日突然やってくるものです。 「何をどう準備すればいいのか分からない」 「そもそも相続税の申告が必要なのか不安…」
こうしたお悩みを抱える方は少なくありません。相続税の申告は期限が決まっているため、早めに必要なことを調べて準備を進めるのが安心です。
今回は、相続税の申告を考えるときに まず調べておきたい基本ポイント を分かりやすくまとめました。
1. 申告が必要かどうかを確認しましょう
相続税には「基礎控除」という仕組みがあります。これは、遺産が一定額までなら税金がかからないというものです。
計算式は次のとおりです。
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
例えば、相続人が2人の場合は 4,200万円までが非課税。 この金額を超える遺産があると、相続税の申告が必要です。
2. 遺産の内容をリストアップ
相続税を計算するためには、財産をすべて把握する必要があります。
-
預金や株式などの金融資産
-
土地・建物といった不動産
-
生命保険金や退職金
- 名義預金(実質的に被相続人のものと判断される他者名義の預金)
-
借金や未払い医療費などのマイナス財産
プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も忘れずに調べましょう。
3. 不動産の評価に注意
土地や建物は評価額によって税額が変わるため、注意が必要です。
-
土地 → 「固定資産税評価額」に倍率を乗じた額又は国税庁が公表している「路線価」で評価
-
建物 → 固定資産税の評価額を使用※土地の評価を路線価方式で行うか、倍率方式で行うかは国税庁のサイトから確認出来ます。https://www.rosenka.nta.go.jp/
4. 期限と提出先を忘れずに
相続税の申告期限は、相続開始(亡くなった日)の翌日から10か月以内。 提出先は、被相続人の住所地を管轄する税務署です。
期限を過ぎると、延滞税や加算税がかかることもあるため、余裕をもって準備しましょう。
5. 必要な書類を揃える
申告にはさまざまな書類が必要です。代表的なものは以下のとおりです。
-
被相続人の戸籍謄本や住民票の除票
-
相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書
-
預金通帳のコピー、不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書
-
遺産分割協議書
「何を用意すればいいのか分からない」と迷ったときは、まずこれらを目安に集めてみましょう。
6. 節税できる制度を確認
相続税には、税額を大きく減らせる制度があります。
-
配偶者の税額軽減 配偶者が相続する財産については、1億6,000万円または法定相続分まで非課税。
-
小規模宅地等の特例 自宅や事業用の土地は、最大80%評価を減らせる場合があります。
こうした特例を使えるかどうかで、納める税額は大きく変わることもあります。
まとめ
相続税の申告を考えるときにまず調べておきたいことは、
1.申告が必要かどうか(基礎控除との比較)
2.遺産の内容と評価方法
3.期限と必要書類
4.節税につながる特例の有無
です。
![]()
税理士・福間より
資料収集や、遺産分割の話合いで思ったより時間がかかるものです。
相続税がかかりそうな場合は10か月以内が申告期限となりますので
はやめに準備にとりかかりましょう。